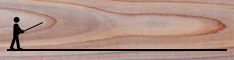木材に油(oil)が乗っているからあーだこーだという方がいらっいますが私は木に油があるとは思っていません。
もし、そこに油(oil)が有ればそれこそ日本は世界有数の産油国と言われることでしょう。
油とよく間違えられるのはエキスではないかと思います。
エキスが少ない木は、鉋で仕上げた際にパサパサ感が残りますし触った感触もピタッとこない事が多いようです。
自然乾燥をメインで乾燥した木材と人工乾燥で乾燥した木材とでは同じ鉋仕上げでも見た目も触った感じも異なります。
どんな人工乾燥機でも自然乾燥に比べて木材に負荷が掛かるでしょう。
人工乾燥は、自然乾燥に比べると急激な乾燥になるために水分と一緒にエキスが出ていったり内部割れが発生したりなど木材には少し酷な乾燥方法だと思います。
様々な人工乾燥機には、木酢と言ってエキスを貯める管がある事が多いです。
その木酢を薄めて木酢液として販売されている事も多いようです。
このエキスが有るか無いかで人の肌に合う合わないほどの差も出てきます。
時間は掛かるけれども急いで希望に沿わない材料を収めるよりも時間と手間が掛かるけれど納得のいく品物を納品する様に心がけています。
木材って設計士さんにはなかなかご理解頂けないのが残念でなりません。
建築士の試験内には、木材についての設問が1~2問だとか…そりゃ勉強しないよなぁ。。。
杉・上小節・カンナ仕上げ・含水率〇〇%位では、残念ながら同じスペックの木材は届きません。
そんなに自分が思うような木材を仕様に入れたいのならもう少し木材を好きになって勉強した方が良いと思います。
私たちが剣道場床で使用する木材仕様書には、原木の選別、製材工程、乾燥工程、加工工程なども記載しています。
例えば、自然乾燥する際の桟の大きさや高さまで指定しています。
もちろん乾燥期間も設けています。
それぞれ意味がって指定しているのです。
一般住宅などを主に設計する設計士さんとお城やお寺を設計する設計士さんどちらの設計士さんとも一緒に仕事はするのですが、どちらかはどれだけ説明しても分かってくれない設計士さんが多いです。
じゃぁ好きにすればと突き放すと、責任の所在が云々閑雲… 最近、設計士さんとの相性が悪いみたいです。